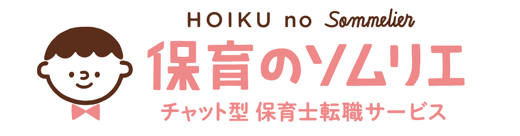少子高齢化社会が問題視される一方で、保育士の需要はますます高まっています。子どもの命を預かるという大変な仕事ですが、子どもが好きな人にとっては絶好の職種だともいえるでしょう。しかし命を預かる仕事だからこそ、プロになるまでの道のりは簡単ではありません。
今回は、保育士になるための資格や受験過程を含め、必要な学歴や合格率についてご説明します。
保育士になるには
保育士の資格を取得するには、大きく分けて2つの方法があります。1つ目は、大学や短期大学などの保育士養成施設を卒業する方法で、2つ目は通信教育などを通して国家試験を受験する方法です。具体的にどのようなものがあるのか、1つずつご紹介します。
・保育士養成施設で学ぶ
保育士養成施設とは、大学・短期大学・専門学校のうち保育士を育てるための過程を備えた厚生労働大臣指定の施設のことをいいます。それぞれ学校で学ぶ期間や学費に大きな差がありますが、いずれも高校卒業後に進学します。
このような保育士養成施設を通じて保育士を目指す場合は、学校を卒業すると同時に「保育士」を名乗ることができます。また、一般の大学や短大などを卒業した場合は、専攻科目に関わらず国家試験を受験する必要があります。
・通信教育で学ぶ
大学などで学ぶ場合に不安になりがちなのが学費でしょう。年間百万円単位の学費を必要とする養成施設に対して、通信教育でははるかに安価な受講料で保育士を目指すことができます。近年では通信教育という方法を選択する人も増加しており、現役保育士のなかには社会人になってから保育士の勉強をはじめたという人も少なくありません。
・独学で学ぶ
最終学歴が短大や大卒の場合は、独学で資格取得を目指すという方法も選択できます。保育士試験の過去問題集などを購入して自主的に勉強することになるので、かなり計画的に進めていかなければなりません。周囲に経験者がいない場合はわからない部分も1人で解決していくことになるので、勉強法としてはもっとも困難だといえるでしょう。
資格取得に必要な学歴
一般的に国家資格といえば、大学や短大など高卒以上の学歴が必要な場合も多いです。しかし保育士資格については、義務教育を終了していれば取得を目指すことができます。つまり、中卒や高卒の人でも保育士になる資格はじゅうぶんにあるということです。
・高校卒業程度認定資格を取得する
最終学歴が中卒の場合は、まず高校卒業程度認定資格を取得する方法が1番の近道でしょう。高校卒業程度認定資格とは、高卒と同等の学歴として国から認められる資格です。つまり高校を卒業していなくても、この試験に合格したことを履歴書に明記することで中卒ではなく高卒であると明言することができます。
何らかの理由で高校へ進学できなかった社会人が受験する場合がほとんどで、保育士だけではなくあらゆる就職活動に有利になる資格でもあります。
高校卒業程度認定資格に合格してから保育士国家試験を受験するには、一定の条件を満たす必要があります。そのなかに「実務経験」という項目があり、高校卒業後に保育施設で実際に月120時間(1日6時間×20日)の勤務を2年以上続けなければなりません。
2年間の総勤務時間は2880時間です。数字で見ると過酷な印象ですが、「現場で勉強しながらプロを目指したい」という人にとっては最適な方法ともいえるでしょう。
・中卒では5年間の実務経験が必要
中卒から保育士を目指す方法としてよく知られているのは、高校卒業程度認定資格を受験することです。しかし実は、最終学歴が中卒であっても保育士国家試験を受験することは可能です。
ところが、当然実務経験の必須時間ははるかに増えてしまいます。高卒での条件が2年間であるのに対し、中卒では5年間、計7,200時間の実務経験が必要になります。もちろん5年間着実に経験を積むのも1つの方法ですが、高校卒業程度認定資格を取得したほうが数年早く保育のプロになることができます。この違いを見ると、やはり高卒程度の学歴を身に着けたほうが賢明といえそうです。
保育士資格の合格率は?
保育士養成施設に進学した場合は、無試験で保育士になることができます。しかし、一般の大学や通信教育を通して保育士になる場合は、必ず国家試験を受験しなければなりません。もちろん、中卒や高卒から保育士を目指す場合も同様です。
保育士国家試験は、全国統一で筆記と実技試験に分けて実施されています。一見簡単に突破できそうな試験ですが、その合格率はかなり低い数字になっています。例えば、平成27年度の保育士国家試験の合格率は、わずか22.8%という結果です(※1)。
子どもの命を預かるプロですから、筆記・実技試験ともに簡単な問題ばかりではないでしょう。さらに筆記試験では9科目すべて6割以上正答してはじめて合格となるため、合格率が低くなってしまうのも納得です。とくに社会人として生活しながら通信教育や独学で勉強している場合は、実質的な難易度がさらに高くなるでしょう。
おわりに
保育士になるには、国が定めた試験に合格することが大前提となります。資格を取得するためにはさまざまな選択肢がありますが、学歴を懸念してプロへの道を諦める必要はありません。義務教育さえ終了していれば、誰でも保育士になることができるのです。子どもたちの安全をより強く保障するために、自分に合った方法で資格取得を目指しましょう。