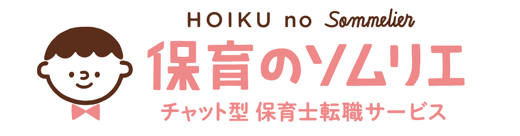保育士の需要が高まるなか、現場で働く人たちはさまざまな悩みを抱えています。そのなかでもとくに多いと言われているのが「人間関係」の問題です。人対人で働くうえでは避けて通れない道ですが、なるべくストレスは小さくしたいもの。今回は、保育士が気になる人間関係について、具体例や良好に保つためのポイントをご紹介します。
退職理由3位の「人間関係」
2014年、保育士有資格者約3万人を対象に行った東京都保育士実態調査では、過去就業経験者の退職理由として「妊娠・出産」「給料が安い」に次いで20.6%の人が「職場の人間関係」と回答しました。また、現在就業者の18%以上が退職意向を示しており、そのうち24.9%の保育士が「職場の人間関係」を退職意向理由に挙げています。(※1)
さらに、現在の職場の改善希望状況では、現在就業者のうち20.3%の保育士が「職員間のコミュニケーション」と回答(※2)。これらは、保育士として現役で勤務している人・退職を考えている人・すでに退職した人のそれぞれが約5人に1人の割合で「人間関係」に悩まされているということになります。
これは東京都での調査ですが、全国的に見ても同じような状況があると言えるでしょう。
どんなトラブルに悩む?
では、保育士の人たちは実際にどんな人間関係に悩まされているのでしょうか。同僚・上下関係・保護者との関係の3点から具体的に紹介します。
・職員同士の悪口・陰口
保育士が悩む人間関係でもっとも多いと言われているのは、職員同士での悪口や陰口です。保育士に限らず、女性が多い職場ではよく見られる問題でしょう。
自分が知らないところで陰口を言われていたり、わざと聞こえるように悪口を言い合っていたり、仲間のことをよく思えない職場で働くのはかなりのストレスを抱えてしまいます。例えば、一生懸命勉強をして子どもたちと向き合えば、先輩から評価される機会も増えるでしょう。しかし、それを見た同僚に嫉妬され、いじめに匹敵するような扱いをされてしまうこともあるのです。
・同僚だからこその上下関係
保育士間の上下関係は、経験の多さで決まる場合も多いでしょう。これは、保育士として働くうえで役職といわれるものが極端に少なく、施設で働く保育士はほとんど「同僚」と認識されるためです。本来ならともに助け合って仕事に熱を向けるべきですが、例えば10年と1年の経験差は想像以上です。
キャリアを積んだ先輩保育士が、新しく入職した新人保育士に対して叱責を重ねることも少なくありません。慣れない業務に苦戦する姿を見て「そんな簡単なこともできないのか」と冷たい言葉を浴びせることもあるでしょう。
・保護者からのクレーム
保育士が悩む人間関係には、職員間以外にも保護者からのクレームにうまく対応できないということも挙げられます。いわゆる「モンスターペアレント」と呼ばれる保護者には、いつの時代でも少なからず遭遇するでしょう。
ベテラン保育士であれば大きなトラブルに発展する前に解決できそうですが、とくに新人保育士にとってはこの上ない難関です。例えばみんなで練習した劇の発表会で「うちの子をもっと目立たせろ」と無理難題を突き付けられることもあります。できないことはできないと理解してくれるまで、あくまで保育のプロとして関係を築き上げていくプレッシャーも重くのしかかるでしょう。
良好な関係を保つには?
保育士はさまざまな面で人間関係に悩んでいますが、とくに職員同士で良好な関係を保つためにできることはあるのでしょうか。一緒に働く時間が長ければ長いほど、良い人間関係を築いていきたいものです。
・挨拶、笑顔などの基本的な行動を見返す
人間関係を良好に保つためにもっとも重要なのは、保育士である前に人間、あるいは大人であることです。出勤時のあいさつや笑顔、「ありがとう」などの些細な言葉や行動を大切にしましょう。
人間関係で悩むことがあっても、まずは笑顔で人と接することを心がけるように。相手が苦手意識の強い人でも、明るく接していれば必ず打ち解けるときがくるはずです。
・悪口に興味を持たない
同僚間で悩むことの多い陰口や悪口には、極力耳を傾けないようにしましょう。自分のことを言われていると分かりながら知らないふりをするのは大変ですが、悪口はあくまでも悪口です。内容が本当のことかどうかは、自分にしか分かりません。
「また何か言っているな」という程度にとどめておいて、そのまま聞き流してしまうのが1番ストレスにならない方法です。また、たとえ腹が立っても決して同じことを繰り返さないようにしましょう。悪口や陰口を連鎖させても、快適な職場になるとは言えません。なかなか難しい対処法ですが、「人は人、自分は自分」という信念を貫きましょう。
・自分なりのストレス発散方法を確立させる
いつも明るく振舞っていても、悪口や陰口に耳を傾けなくても、ストレスはどうしても溜まっていきます。これは人間関係だけが原因ではなく、保育士でなくても社会で働くうえでは仕方のないことです。
ストレスをためないように努力するのではなく、ストレス発散ができる場を確保しておきましょう。趣味に没頭したり、家族や親しい友人と話をしたり、悩みを相談する機会も必要です。保育に関して相談できる人がいないときは、学生時代の同級生や先輩に声をかけてみるのも良いかもしれません。自分が「発散できた」と思える環境を作って、無理なく良好な人間関係を保てるよう意識してみましょう。
・飲み会を開く、参加する
保育士同士の人間関係に悩んだら、思い切って食事会や飲み会の場を設けるのも1つの方法です。プライベートに仕事を持ち込みたくないと思うかもしれませんが、普段とは違う雰囲気の中で同僚と言葉を交わすことで、思わぬ一面が見えてくることもあります。
お酒を飲むことで、自分も相手も言いづらかったことが言いやすくなるかもしれません。はじめて参加するときは少し不安になりますが、思い切ってプライベートでの関係に踏み出してみるのも人間関係を良好に保つために大切なポイントです。
おわりに
保育士が悩む人間関係には同僚や上下関係、保護者との関係がありますが、一人ひとりが少し意識するだけで良好な関係を築くことができます。過度にストレスをため込まず、マイペースに快適な保育士生活を送りましょう。