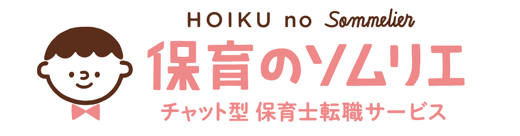1歳児クラスから2歳児クラスに多く見られる子どものトラブル「噛みつき」。子どもの体に残ってしまった歯形の跡を見る度に、「また防ぐことができなかった」と落ち込む保育士さんも多いのではないでしょうか。
私も1歳児を担任していた時に、毎日のように噛みつきが起こり頭を抱えていた時期がありました。この記事では、私の経験を踏まえて噛みつきの理由や対処の方法などを紹介していきます。
なぜ噛みつきが起こるのかもう一度考えてみましょう。
気がつかないうちに「噛みつきをする子ども=困った子ども」と思い込んではいませんか?子どもが噛みつきに至るまでの状況はさまざまです。一度立ち止まって、どうして噛みつきが起こってしまったのかを考えてみましょう。
1.気持ちを言葉にできないケース
1歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちはまだまだ言葉が発達途中であり、かつ自我が芽生え自分の欲求を何でも通したがる時期です。お友達との関わりが増えてきた1歳児後半の子どもたちの中には、自分の気持ちを上手く言葉で伝えることができず、噛みつくことで表現しようとしてしまうことがあります。
特徴としては、噛みつきの多くが友達と関わっている時に起こっています。友達とやり取りをする中で「かして」、「みせて」、「いれて」、「まだ(玩具を)使っている」等が言えずに噛みついてしまいます。
2.関わり方がわからないケース
興奮してしまって噛みつく、挨拶やじゃれているつもり、また遊びの一環として噛みついてしまうこともあります。噛みついてしまう子どもにとって、噛みつくという行為は愛情表現のひとつになっていることもあります。
3.子どもが不安定になっているケース
お母さんが妊娠していたり、子ども自身が疲れていたり気持ちが満たされていないことで心が不安定になり、自分を守るために噛みつくこともあります。
もし、同じ子が複数回噛みつきをしているなら、その時の状況を詳しく振り返ることで、その子が噛みつきに至るまでの状況や噛みつきをしてしまいやすいタイミングをぼんやりと把握することができると思います。そして、それは次回その子の噛みつきを防ぐことに役に立つことでしょう。また、担任同士でその情報を共有することも大切です。
(例 Aちゃんは自由遊びの時に玩具の取り合いで噛みつくことが複数回あった。これからは自由遊びの際はAちゃんの傍にいて、噛みつきそうな時に間に入って言葉で代弁しよう)
噛みつきを未然に防ぐにはどうしたらいい?
噛みつきに至るまでの状況を整理しましたが、では噛みつきを未然に防ぐにはどうしたら良いでしょうか? 噛みつく子が噛みつきをよくしてしまうタイミングやシチュエーションが分かったら、その時には特に目を離さないようにしましょう。
1.気持ちを言葉にできないケース
⇒友達との関わりの際はいつでも手や声が届くところから見守りましょう。噛みつきをしそうな時は間に入り、噛みつきをしそうになった子どもの気持ちを代弁します。繰り返していくと、自分の気持ちを理解してくれた大人への安心感からトラブルの時に保育士を探して助けを求めたり、自分の言葉で伝えたりできるように成長します。
2.関わり方がわからないケース
⇒噛みついてしまう子どもと保育士が一緒になって友達と関わるようにしましょう。(例 挨拶代わりに噛んでしまう子どもなら、噛んでしまう子と保育士が一緒になって友達に言葉で挨拶をしにいく)
3.子どもが不安定になっているケース
⇒個別にスキンシップをたくさんとっていく。子どもの気持ちを共感して、受け止めていく。
以下、噛みつきの状況や理由がさまざまでも共通して言える、噛みつきを未然に防ぐポイントをまとめました。
・子どもの動きから目を離さない。
・担任同士で情報を共有し、見守っていく。
・噛みつきが多く見られる子へすぐ手や声が届く範囲に保育士がいるようにする。
・子どもが一か所に固まりすぎないように心掛ける。
・噛みつきが多く見られる子に特によくスキンシップをとり、安心感を得られるようにする。
噛みつきが起こった時の対処方法
どんなに噛みつきを防ごうと努力しても、防ぎきれずに噛みつきが起こってしまうこともあります。そんな時、どのような対処をしていけばよいでしょうか。
・噛みつかれてしまった子どもへの対応
噛みつき跡が残らないように手当てをしながら、噛まれて痛かった子どもの気持ちを共感しましょう。この時に、噛んでしまった子の気持ちも伝えましょう。
【手当ての仕方】
噛みつきの傷には口の中の雑菌がついていることもあります。一見傷や出血がないように見えても、皮膚が傷ついている可能性もありますので、必ず流水で洗いましょう。その後、速やかに患部を冷水や氷水などで15分程度冷やしてください。
この時、患部を揉まないように気をつけてください。噛みつきの傷は内出血と炎症であることが多いです。揉むことで悪化させてしまうことがあります。
冷却ジェルシートの効果は氷水と比較すると低く、シートで傷が覆われると傷の様子を確認することが難しくなるのでお勧めはしません。
・噛みついてしまった子どもへの対応
一方的に噛みつきはいけないことだと叱るのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながらも、「噛みつく」という行為は友達を傷つけてしまうことであるということを伝えましょう。噛みつきがあってしばらくしてから話しをしても子どもはなんのことだかわかりません。噛みつきがあった直後に伝えることが大切です。
(例)「AちゃんはBちゃんの使っているこの玩具が使いたかったんだね。でも、噛んでしまったら、Bちゃんは痛いよ。そういう時は貸してって言おうね。」
・保護者への対応
園によって方針が異なる場合がありますので、園の方針に従って保護者への対応を行ってください。
噛まれてしまった子どもの保護者には、保育士がついていながら防ぐことができなかったこと、誠意を持って謝罪しましょう。保護者は、自分の子どもがいじめられているのではないか、保育士にきちんと見てもらっていないのではないだろうかと心配になるかと思います。そんな保護者の気持ちも受け止めて、園での対策や子どもの現在の発達の様子についての話をすると安心してもらえるかと思います。保護者との信頼関係は一朝一夕には築けません。日頃から子どものさまざまな話をすることで、良い関係を保っていきたいですね。
噛んでしまった子どもの保護者への対応は園によって差があるかと思います。もし、噛みついたことを保護者に話すのであれば、保護者を責めるように伝えるのはNGです。子どもの園での様子の中に噛みつきがあるということ、園と家庭で協力して噛みつきを減らしていきたいと思っていることの2点を丁寧に話していきましょう。
おわりに
乳児を担任する保育士の悩みの種である子どもの噛みつきですが、子どもが噛みつきをしてしまうのには理由があります。そして、言葉の成長とともに噛みつきによるトラブルは必ず減っていきます。保育士同士で情報を共有し、連携を取り合いながら、子どもの気持ちに寄り添った保育をしていきたいですね。