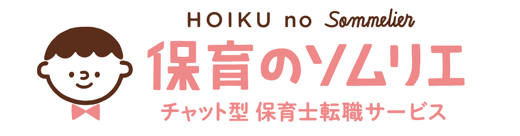保育士の皆さん。多忙な日常の中、園児たちについ大きな声を出してしまうこともありますよね。
「何度言ったら分かるの!」
「やめなさいっ!」
「どうして〜するの!」
では、その大声、本当に園児たちを思ったしつけになっているのでしょうか?
保育士の一言というのは、園児たちにとってとても印象に残っているもの。その日、次の日、時には一生を左右することさえある一言かもしれません。そこで今回は、保育士の皆さんに、しつけに繋がる上手な叱り方をご紹介します。
1.叱ると怒るの違い
しつけにおいて、保育士がまず考えておきたいのが”叱る”と”怒る”の違い。その場での結果は同じでも、園児たちに与える印象は大きく異なります。
怒るは感情の爆発
まず、”怒る”というのは感情の爆発です。
園児たちが言うことを聞かない、自分勝手に行動をする。「やめなさい!」、つい大声を出したくなる気持ちも分かります。確かに、大抵の園児たちは大人の大声に反応して止まります。
ただし、あくまで大声にびっくり、または萎縮して止まっているだけです。なぜ怒られているのか、理由も分からないまま行動をやめているだけ。理由が分からなければ、園児たちは繰り返します。保育士の目を盗んで、時には保育士の前でからかうように。しつけにならないばかりか、保育士のストレスになるので要注意です。
叱るは計算と結果
次に、”叱る”と言うのは計算と結果です。”なぜその行動がいけないのかを理解させる”ことが目的です。保育士の対応に対して、園児たちがどのように反応するのか。冷静に計算、予想した上での対応がいわゆる”叱る”ということです。
計算の上で対応しても、必ずしも予想通りに反応するとは限りません。しかし、園児たちのことを思って、トライ&エラーを繰り返すことで、園児たちを理解しようと、冷静に考えることで自然と叱り方が身につきます。叱り方さえしっかり身につけば、園児たちはいけない行動をしなくなります。
2.叱り方のQ&A

叱り方の基本は”園児たちがなぜ問題行動をするのか”を想像してみること。では、しつけに繋がる叱り方として、いくつかの状況をもとに紹介していきましょう。
喧嘩しているとき
園児たちが喧嘩しているとき、「ダメ!ごめんなさいして!」と対応していませんか?
園児たちが喧嘩するには、些細なことでも原因がかならずあります。まずは何が原因で喧嘩しているのか、当事者の園児たちに聞いてあげましょう。もし興奮していて話せないなら、他の園児たちに聞き込みするのもありです。お互いの言い分を十分に聞いて、”受容”と”共感”をしてから次の対応に。お互いに心の整理ができていれば、「ごめんさないしよっか」で素直に謝れます。
失敗をしたとき
園児たちはまだ成長過程。ついうっかりで失敗することもあります。
例えば、昼食中にお盆をひっくり返したり、トイレを我慢して失敗したり。体は小さいですが、心は大人が思っているよりも発達していて一人前。大人と同じようにプライドがあり、失敗を周りに知られたくないものです。少なくとも見せしめのように、大勢の前で叱るのはやめましょう。
園児たちの失敗は保育士がさっとフォローして、その上で言葉かけを。まずは空間を普段の状態に戻してから、何がいけなかったのかを伝えます。「次はこうすると良いね」と、次に失敗しないようにするのがしつけです。
ルール違反をしたとき
園児たちは興味本位でついルール違反もします。そんな時、「何回言ったら分かるの?どうして〜するの?」と声を荒げていませんか?
園児たちにとって、保育士の作ったルールというのはよくわかりません。朝の会などで、「今日も仲良く〜」と復唱させても何となくで言わされているだけ。年少さんならまだしも、年長さんにもなると言葉も達者になり揚げ足を取ります。いっそのこと園児たちに、基本的なルール作りをしてもらうのも1つの手。自分たちの作ったルールであれば、園児たちも自然と守ってくれます。たとえそのルールが、保育士に誘導されて作らされたルールであってもです。
危険なことをしているとき
しつけにおいて、大声が唯一有効とされるのが危険な状況のとき。
ハサミを振り回しているとき、コンセントで遊んでいるときなど、園児たちの”命の危険”につながるようなときは大声を出すべきです。
というのも、危険な状況というのは理由を伝えている暇がありません。まずは危険な行動をやめさせて、その後にしっかり叱りましょう。「ダメ!」「危ない!」「ストップ!」など短い単語で大きな声で伝えます。ちなみに、「ストップ!」はとても響きやすく、おすすめの単語です。普段は優しい保育士の大声ほど、園児たちに響くものはありません。
3.年齢別のしつけ
ここまで、状況別の叱り方について、しつけについて紹介してきました。
ただ、叱り方というのは年齢によって、年少と年長によっても違いがあります。
2歳児さんまでは感情的に
2歳児さんまでは言葉の理解力が未発達です。
基本は3単語以内、「お手て、痛くなるから、やめようね」のように。できればどこかに”感情的”な単語を挟むと、より理解しやすいです。例えば、「悲しい」「痛い」「びっくり」「楽しい」「嬉しい」など。
園児たちの普段の話し方を意識すると、叱り方の参考になりますよ。
3歳児さん以上は理論的に
3歳児さん以上になると、少しずつ言葉の意味を理解できます。
基本は4単語以上、「お部屋で、走ってると、お友達に、ぶつかって、危ないから、やめてね」と。できる限り”理論的”に、何がどうなってどんな結果が待っているのか。ただし、難しすぎる言葉だと理解できないので、あくまで園児目線です。
命令口調になると反発しやすいので、”お願い口調”にするとなおいいです。
4.おわりに
今回は、保育士に知ってもらいたい、しつけに繋がる叱り方をご紹介してきました。毎日、園児たちと関わっていると、忙しさからつい感情的になるのは仕方ないです。しかし、感情的に怒っても、まず園児たちの心に響くことはありません。叱り方で大切なのは、”常に冷静に状況を把握して対応する”ことです。
保育士の感情は園児に伝染します。特に、怒りや不安といった負の感情は。まずは心を落ち着かせて、ゆっくりとでも状況を把握することから挑戦しましょう。普段は優しいけどしっかり叱れる、園児たちから信頼される保育士を目指してください。