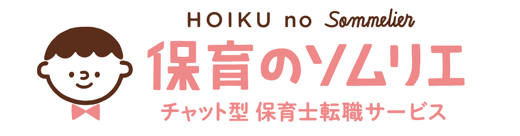保育士にとって園児たちと遊ぶことはとても重要な仕事です。
しかし、梅雨の時期、雪の時期になるとなかなか外では遊べません。そんな時、保育士の皆さんからの提案が、園児たちの1日の活動内容に大きな影響を与えます。園児たちが楽しく、元気に過ごせるかは皆さん次第なのです。
そこで、今回は室内だからこそできる、手足や頭の体操になる室内遊びをご紹介します。手足をいっぱい使って元気に、頭をウンウン唸らせて成長につながるものばかりです。ぜひ、これからの室内遊びの参考にしてみてくださいね。
手足を使った室内遊び3選
園児たちは手足を使って動き回るのが大好きです。外のように走り回るのは難しくても、ちょっと工夫すれば室内でも手足を使って元気に遊ぶことはできます。
・真似っこゲーム
名前の通り、真似っこをして遊ぶゲームです。
<遊び方>
1. 保育士がお題を出す
2. 園児たちが保育士の真似をする
例えば、保育士が「〇〇ちゃん!こんなことできますか〜?」と特定(またはグループ)の園児を指名してから、お尻フリフリしたとして。園児(〇〇ちゃん)が「こんなことできますよ〜!」と保育士の動きを真似っこしてお尻フリフリするだけ。
<ポイント>
・初めの2,3回は保育士がお題を出す
・お題は園児たちの年齢に合わせたものを選ぶ
・慣れてきたらスピードを上げたりテンポを変えたりする
真似っこゲームは手足をいっぱい動かしつつ、限られたスペースでも十分にできる室内遊びです。お題さえきちんと選んであげれば、年少さんから年長さんまで年齢に関わらず楽しめるのもポイントです。
・5mおしり走
お尻だけを使って前に進む室内遊びです。
<遊び方>
1.園児たちは体育座りで横一列に並ぶ
2.保育士の合図でお尻だけを使って前に進む
机やおもちゃを移動させれば、クラス内でも5mの直線を作るのは難しくありません。あとは、「よーい、どん!」と保育士の合図でスタートするだけ。競争するのもいいですが、慣れてきたらお尻だけで移動する追いかけっこをしてみてもいいです。
<ポイント>
・手や足は床につけないようにする
・両手を大きく動かすと前に進みやすい
・横の子にぶつからないよう配慮する
クラス内だけでなく、体育館があるなら広い空間でするのも。クラス対抗にしたり、年齢別でまとめて大人数にしたりしても盛り上がります。今回は5mにしましたが、年齢によって3mや8mに調整するとみんなで楽しめますよ。
・カラダじゃんけん
カラダを大きく使ってするじゃんけんです。
<遊び方>
1.保育士の「じゃんけんぽん!」の掛け声に合わせて
2.園児たちはカラダで”グー・チョキ・パー”を表現する
例えば、グーは体育座りのように、チョキは手足を前後に大きく広げて、パーは手足を大きく左右に広げてなど。クラスを2つのチームに分けて左右一列に並べて、チーム対抗の勝ち抜き戦にするのもおすすめです。
<ポイント>
・初めは保育士の掛け声に合わせてする
・慣れたら園児たちでポーズを自由に決める
・手足が横の子に当たらないよう配慮する
カラダじゃんけんのポーズにこれといった決まりはありません。両手だけ、両足だけでグー・チョキ・パーを表現することも。園児たちの自由な発想に任せてみると、思いもよらない面白いポーズが生まれるかもしれませんよ。
頭を使った室内遊び3選
手足を使って思いっきりカラダを動かすのもいいですが、せっかくの室内遊びですから頭を使ったものにしてみるのも。お外ではできない、室内遊びならではの頭脳ゲームをしてみるのも面白いです。
・60秒ギリギリタイム
60秒ぴったりになるよう予測するゲームです。
<遊び方>
1.保育士の掛け声でストップウォッチをスタートする
2.園児たちは60秒経ったと思ったときに手を上げる
年長さんたちは小学校に向けて、より時間感覚を磨いておく必要があります。60秒ギリギリタイムは時間感覚を楽しみながら磨ける室内遊びです。ちょっとした時間にもでき、園児たちの集中力を高めるのにも役立ちます。
<ポイント>
・キッチンタイマーやスマホ(タイマー)でもできる
・時計が目に入らないように立ち位置を意識する
・他の子の邪魔にならないよう声は出さないようにする
60秒が難しいようなら、最初は10秒からでも。慣れてきたら20秒、30秒と伸ばしていくといいでしょう。感覚の鋭い園児たちだと、意外に60秒ピッタリがでることも。ピッタリ賞を作ると園児たちの競争心を刺激できます。
・後出しジャンケン
後出しで勝つように手をだすじゃんけんです。
<遊び方>
1.保育士が「じゃんけんぽん!」の掛け声で手を出す
2.園児たちはワンテンポ遅れて勝つように手を出す
例えば、保育士がグーを出したとして。園児たちはワンテンポ遅れてパーを出すなど。後出しジャンケンでは状況を正しく把握し、素早く回答を導きだす思考力が養えます。「あっとだしじゃんけん〜」とテンポよくするとより楽しいです。
<ポイント>
・初めはゆっくりのテンポでする
・慣れてきたら勝ち負けを指定する
・失敗した子から座るようにする
慣れてきたら「負けたら勝ちよ〜」、「あいこが勝ちよ〜」のようにルールを変えてみるのも面白いです。「勝ったら負けよ〜」とあえてちょっと意地悪なルールにしてみると、より園児たちの思考力を刺激できます。
・○□△ゲーム
左右で異なる形を表現するゲームです。
<遊び方>
1.保育士が表現する形を指定する
2.園児たちは左右で異なる形を表現する
例えば、保育士が「右手は丸を、左手は三角を」と指定したとします。園児たちは指定された通りに右手で丸を、左手で三角をと。○□△ゲームは認知症予防にも使われるほど、脳の刺激にいいとされる室内遊びです。
<ポイント>
・初めはゆっくりでも表現できるようにする
・慣れてきたら途中で指定する形を変更する
園児たちは頭がまだ柔らかいので、大人よりも簡単にやってくれます。そこで、初めは三角を指定しつつ、途中で丸に変更したりなどあえて意地悪をしてみましょう。園児たちの脳の発達と、集中力の向上に役立ちます。
おわりに
室内でも楽しめる、手足や頭を使った遊び方についてまとめてみました。手足を使ったものは室内でも元気いっぱいに動けるもの。頭を使ったものはウンウン唸って、園児たちの脳の発達や集中力を向上させてくれるものです。
室内遊びで大切なのは、園児たちの年齢や性格などに合わせた内容を提案すること。あまりに簡単すぎても、難しすぎても飽きられてしまいます。ぜひ、園児たちみんなが楽しめる、室内でも元気になれる遊びを提案してあげてください。