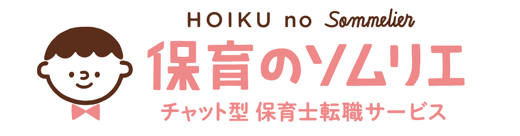“モンスターペアレント”、保育士なら誰しも耳にしたことがあるはず。
日々、保育園には保護者からの様々な相談、もといクレームが寄せられます。「これって本気で言ってるの?」と、耳を疑いたくなるようなクレームまで。保護者をモンスターと言うのは、失礼と思いつつも…仕方のないことも。しかし、保育士の対応ミスによって、保護者がモンスターペアレントになるケースもあります。ちょっとした気遣いができていれば、何事もなく解決していたケースもあるのです。
今回は、保育園に寄せられるクレーム事例と、親対応のコツをご紹介します。
保育園はクレームの宝庫?
前提として、ほとんどの保護者は保育士の皆さんのことを信頼しています。「モンスターと思われたらどうしよう」と、相談できない保護者もいるほどです。
親対応でモンスターペアレントが育つ
日々、保護者からの相談やクレームに対応しているかと思います。
では、これまでの親対応を振り返って、保護者たちは納得していたでしょうか?不安そうな親、不満げな親、中には対応したことで怒りだした親もいたのではないでしょうか。保護者がクレームを言ってくるのは、我が子のことでなんらかの不安があるから。保育園の対応が不十分だと感じたからこそ、解消するために要求が過剰になってしまったのです。初めからモンスターペアレントだったのではなく、保育士の皆さんの親対応がそうさせることもあるのです。
保育園で実際にあったクレーム事例
もちろん、初めからモンスターと言わざるをえない、耳を疑いたくなるクレームもあります。
例えば、保育園では以下のようなクレームが、実際に数多く寄せられています。
「うちの子が主役じゃなかったから、お遊戯会をやり直してください」
「席替えのとき、隣の席は仲のいい子だけにしてください」
「保育園で汚したんですから、衣類はそちらで洗濯してください」
「うちは怒らない教育方針なので、絶対に怒らないでください」
上記はまだ良いもので、中には保育園を裁判所に訴えるような内容もあったそうです。保育園がいかにクレームの宝庫か、保育士の皆さんの苦労が伝わってきますね。
モンスターペアレントを育てる塩対応
ありえないクレームは別として、大抵のクレームは適切な親対応で解決します。反対に、塩対応をしてしまうと、保護者をモンスターペアレントにしてしまうかもしれません。
否定から入る
新人の保育士によくあるのが、保護者のクレームに否定から入ることです。「でも」「だって」「違います」「そんなことないです」「できません」と言ってはいませんか?
保護者に限らず、人間というのは他人から否定されると無意識に自己を守ろうとします。自己を守るには相手を倒すのが簡単で、つい感情的に攻撃的になってしまうものです。親対応でクレームが大きくなるのは、ほとんどが初期対応をした保育士の言動です。
早口になる
保育士の皆さんも人間ですから、興奮すればつい早口なることもあります。クレームでは保護者が興奮し、早口でまくし立ててくることも珍しくありません。そんな保護者の雰囲気に飲まれて、保育士までも興奮してしまうことも。相手の発言をすぐに訂正したい、言い分を伝えたいと早口になる訳です。
早口で対応された側は、発言に割り込むためさらに早口で応戦することに。言い合いがヒートアップすると、解決するはずだったものも難しくなります。
曖昧な対応をする
親対応でもっともやってはいけないのは、”曖昧な対応をする”ことです。
保育園全体として、保育士として、大人として、様々な立場があります。親対応では立場を意識して、当たり障りのない対応をしてしまいがちです。しかし、保護者からすれば、”曖昧な対応=何もしていない”と同じです。正直、「できるのか、できないのかはっきりして!」と余計に不安にさせます。保育士の曖昧な対応が不満に、保護者をモンスターペアレントさせるのです。
保護者に信頼される神対応

保育園では信頼される保育士、信頼されない保育士の二極化が起こりがち。
では、保護者から信頼される神対応とはどのようなものかご紹介しましょう。
事実を認める
まず、保護者のクレームに対して事実を認めてください。もちろん、保護者の要求をすべて飲むということではありません。
あくまで話を聞くこと、要求や要望に耳を傾けること。「そうだったんですね」と、聞き役に徹するだけで十分です。”聞いてもらえた”という事実が、保護者の興奮を抑えてくれます。また、聞き役に徹することで、状況を正しく把握できます。
素早く行動する
次に、状況を把握できたら、できることから素早く行動します。その場で回答できるものはして、できないものはその理由を。保育士個人の裁量で、できる範囲で行動すればいいだけです。小さなことでも目に見える行動があれば、保護者も安心します。”できること”と”できないこと”を明確にするだけでも効果的です。
結果を伝える
最後に、後回しにしたものについて、結果を伝えることも忘れずに。”できない”と伝えたものでも、保育園として何らかの対応をする必要があります。職員会議にかけるとか、検討してできることには対応してみるとかです。
保護者はクレームに対して、常に何らかの結果を求めています。結果のないままでは不安が増すので、忘れずに伝えましょう。
おわりに
保育園によくあるクレーム事例と、親対応の基本姿勢についてまとめました。理不尽なものでない限り、クレームというのは保護者の不安が表面化したもの。初動対応さえしっかりしていれば、大抵のクレームは問題なく解決します。
親対応で大切なのは”保護者の話を聞き、できることから素早く行動する”こと。適切に対応できれば、保護者から信頼できる保育士さんとして頼りにされます。”クレームは成長するためのステップ”と考えて、積極的に挑戦してみてください。
余談ですが、1人で対応できないときは他の保育士に相談するのがおすすめです。抱え込んでしまったばかりに、保育士としての自信がなくなることや、病気になってしまっては元も子もありません。柔軟に対応し、保育士生活を充実させてくださいね。