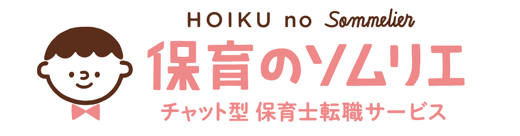国際化が進み英語教育が重要視される中で、小学校5年生からの英語科目が必修となりました。現在、もっと早期化する動きもあるようです。それに伴い、保育業界でも乳幼児期から英語で保育をする「英語保育」が注目されています。この記事では、「英語保育」とはどんな保育なのか、取り入れている施設ではどんな人がどんな風に働いているのか、紹介していきます。
英語保育とは?
英語保育といっても、園やサイトによって定義が少し異なっていることもあるのが現状です。名前もバイリンガル保育、英語保育などさまざまな呼び方があり、内容も1日英語漬けの生活を送る保育や英語と日本語が半分ずつの保育、さらに基本的には日本語で生活していて決まった日に英語で遊ぶ保育などがあります。
ここでの英語保育とは、朝の登園での「おはよう」から、降園での「さようなら」までの園生活すべてのやり取りを英語で行う保育のことを指します。英語を学ぶのではなく、英語で生活をするというイメージで、自然に身に付いていく英語を目指しています。基本的に、子どもたちは登園してきたら、日本語禁止のルールになっていて、先生たちに英語で話しかけるのはもちろん、友達同士の会話も英語で行っています。
英語保育を取り入れている施設について
Q&A
―園生活すべてのやり取りを英語で行っている園。何歳児から受け入れ可能なのでしょうか?
園によって異なりますが、2歳児から受け入れをしている園が多く見られます。1歳児から受け入れをしている園もありますが、少ないようです。乳児を対象に、親子クラスを決まった曜日に行っているところもあります。
―クラス編成や職員配置はどのようになっているのでしょうか?
ひとつの学年またはクラスをネイティブの外国人の先生と日本人の先生で担任しています。なので、人員配置は一般の保育施設よりもやや多い傾向です。ネイティブの外国人の先生と日本人の先生が話し合って、日々の保育計画を作成し、保育を行っています
―具体的な日本人アシスタントの仕事内容とは?
朝の子どもたちの受け入れ、帰りの送り出し、保育環境の整備、保育の用意、保護者対応、月案や週案の作成、行事の準備、一緒に担当しているネイティブの先生とのミーティングなどがあげられます。一般的な保育施設とほとんど変わらないと思います。ただ、保育の現場でのメインは常にネイティブの先生であることが多く、日本人はあくまでアシスタントです。
日本人が園の基準を満たすバイリンガルである場合は、バイリンガル日本人がメインで保育をするところもあるそうです。その場合、日本人にはネイティブの先生と同等レベルの高い英会話能力が求められます。
―行事はどんなことをしているの?外国のイベントを取り入れているの?
園の方針によってさまざまですが、日本の行事(子どもの日、七夕、節分やひなまつり)も園行事として行うところもあります。外国の行事であるハロウィンやクリスマスは、他の日本の施設よりも気合いが入っていて、盛大に行っているそうです。
英語保育を取り入れている施設で
働くメリットとは?
1.外国人スタッフと一緒に働くので、コミュニケーション力が身に付きます。特に英語のスピーキングとリスニングの力があがります。
2.さまざまな国の文化を知ることができます。
3.外国人は基本的に残業を好みません。それに伴って、働く日本人も残業が少ない傾向にあります。
4.人間関係も良好なところが多いです。国や言葉の違うスタッフが働いていることから、違いを認め、理解し合おうとコミュニケーションを活発に取る雰囲気があるからだと考えられます。
必要なスキル、資格
求められる英語力は園によって異なります。日常英会話レベル以上を求めるところもありますし、中にはビジネスレベルの英語を求めるところもあります。
日常英会話レベルを求める園では、高度な語学力より、現場(保育施設)での経験の有無や保育士資格や幼稚園教諭免許を取得していることを重視する傾向があります。保育現場で使われる英語に特化した保育英語検定という資格もあるので、取得を目指すのも良いかもしれません。
おわりに
なかなか想像がつきにくい英語保育ですが、なんとなくイメージが湧きましたか?これからますますグローバル化する時代の流れを考えると、そう遠くない未来、英語保育が当たり前となることも…。英語に興味のある方や英語が得意な方は、武器となることもあるでしょう。選択肢のひとつとして、英語保育を考えてみてはいかがでしょうか。